�n���̏��_�̖��������̐��E�y�C�V���^���A�z�́A
�����Ȏ��R�A�`���̔ޕ��̈�ՁA�Α���̏�Ԃƒ����݁A
�����āA����Ɩ��@��w�i�Ƃ������قȕ����E���j���N�ɘj���ė��s���đ����Ă����B
�u������Ⴀ�����b!!�v
�l�X�̐����ֈ�ʓI�ɕ��y����y���@�z�Ƃ́A
�����̓��֜߈˂����鎖�Œ��╗�͂��N�������̃G�l���M�[�͊w�ł���A
�N�����g���閲�̗͂������B
�u�ł����݂��\�\�B�b!!�v
��ʓI�ɕ��y����y���@�z�́A���Â̐̂ɑn���̏��_�y�C�V���^���z���^�������b�ł���Ɠ`�����A
���݂ɂ��S�m�S�\�̏ے��Ƃ��āA���_��M���镗�K�͐₦�Ȃ��B
�u�̂͂��O�̕����낤�b�A�f�������b!?�v
�u���炸���̓N���[���q�b�g�����Ă���ɂ��₪��A�u���[�U�[�b!!�v
�y���@�z�����ӂƂ�����j����ށy�C�V���^���A�z�ɂ����Ė��͂̋���́A
���̂܂ܐg���I�K�ʂ̕\��ƍl�����A�ߋ��A��҂ɑ�����J�I�ȍ��ʂ�����������������A
���̗͗B��̕��Q�Ƃ��āA���N���܂�Ă����B
�u���̈��Łc���܂肾�������������b!!!!�v
�u�j��������o���ɂ��݂����A���̈��Ō��߂₪�ꂥ�����������b!!!!�v
�₪�Ă��̍��ʂ��A�y���@�z�̌������i�I�ɐi�߁A
���吭������ՂƂ���Љ��ΓI�Ȕ����͂�L����܂łɎ������k���̑卑�y�A���e�i�z�̐s�͂ɂ���ēP�p����A
���݂܂łɂ́A���ނׂ����K�Ƃ��Ėw�Ǘ��������Ă���B
�u�u���b�c�c�c���������������������������b!!!!�v�v
�\�\�ł��A��قǂ��玩�R�����ő剹����グ�Ė،������킹��A���@�̃}�̎��ɂ����̖������̓�l���A
���̎���ɐ��܂�Ă����Ƃ��Ă��A���ނׂ����ʂɏ������Ƃ́A
���ނׂ����ʂɐS��敾�������Ƃ͓���v���Ȃ����B
�u�I���b�I�@�ł����ݐ̂͂��O�̂ق������b!!�v
�u�\�\�ʂ�b!?�@���܃b�c!?�v
�h�K���A�Ƃ����i�C�̗ǂ������Ƌ��Ƀu���[�U�[�E�j�E�W���}�_�n���̔]�V��
�f�������E�p���b�V���̖،����@�����܂ꂽ�B
�u�����c�������������c�܁A�Q�������c�v
�u����łT38�풆218��217�s3�����c�܂����̈�����[�h���ȃb�v
�s�k���đ�ɓ|�ꂽ�u���[�U�[�ׂ̗ցA�f���������g�����o�����B
���݂��Ɍ��ő����Ċz�ɂ͑嗱�̊����������ł��邪�A
�S�͂��o���s�������̂��A�g��������͑u�₩�ȏ݂Œ]��ł���B
�u�������傤�c�f�������A�܂��r�F�グ�₪�����Ȃ��`�B
�@���O�A�������������������t�F�C���g�g���₪�����ȁv
�u�����H�@�����c�������̋Z���c�B
�@����Ⴀ�A���Ȃ����p���h�[���֏o���������A
�@�W�F�}�������Ă����I�b�T���Ǝ����������ɖڂŌ��Ċo���āc�v
�u���ꂾ���ōČ������܂����O�ɑ��h���邾���A�O���ꂿ�܂������c�B
�@�F�X�ȈӖ��ŃX�Q�F��A���O�́c�v
�u������A���̉�肭�ǂ��������͂�c�v
�����̍��Ə̂���邾�������āA���̍��c�y�t�H���Z�i�z�̎��R�������ʂ�̑N�₩���́A
���E�k�`�ɋ������l��D������݁A�����������炵���B
�Љ�]������݁A�t���Ƃ��Ėłڂ���Ă��܂����鋫�y���[�����g�z�̎��R��
���E�ی�Ɏw�肳���قǔ���ŖL�x�������Ɠ`������邪�A
�y�t�H���Z�i�z�̐[�������ĕ����Ă͂��Ȃ����낤�B
�u�\�\���Z�����`���v
���̋Z���A���̑̎J�����Ɖ��X�ƌJ��Ԃ���l�ցA�ǂ����������琺��������ꂽ�B
�u���̐��́c�E�F���f�B����b�I�v
�u�Ȃ�Ő�������ꂽ����肨�O�̂���ɔ�������c�v
�����o���̂��鐺�������ۂ�A�K�o�b�ƋN���オ��u���[�U�[�B
����ɑ����Ȃ���A�f�������͕���̗��ߑ���f���o�����B
�����ɔ����t����ꂽ���R�����̓�����ł́A
�܂��܂��c���̎c�鏭�����傫�������U���ăf�������ցu����ς肱���ɂ������`�v�ƌĂт����Ă���B
�u�E�F���f�B�����A�܂�������ƃJ�����N�Ȃ�����ȁ`�v
�u�c������������肾��A���O�B
�@����̍����Ŋ�������قnj��I�ɕς�����c�v
�u�[���B�����荡���A������薾���A���̎q���Y��ɐ������Ă�����I
�@�[���A�E�F���f�B�����͂������ĉ����b!!�v
�u�Ў肶�ᐔ�����˂����炢�ɔN�̗��ꂽ�K�L�ɐF�ڎg���ϑԂ�
�@�s���̌�q���ł���g�R���̋R�m�T�}����Ă��琢��������ȁc�v
�삯����Ă���E�F���f�B�ւ��炵�Ȃ���Ŏ��U��Ԃ��e�F�ɑ��āA
��x�ڂ̐[���Q����f���o���f���������������A
��������Ȃ薅�ɋ��߂����ăh�X���ƈꌂ�������A
���h���ɋ}�������ł��ꂽ�ɂ݂ɐg�̂����̎��ɐ܂��Ė�₵���B
�u�c���A�����Ȃ艣�肩�����Ă��邽���A
�@�䂪���Ȃ���A�ȁA�Ȃ��Ȃ������L�[����˂����c�v
�u�z���g�̃����L�[�Ȃ��Z�����Ɍ���ꂽ���Ȃ�����I
�@���`�ꂳ��A�J���J�������!?�v
�u�c�p���t���ȃE�F���f�B�������f�G���Ȃ��v
�u�u���[�U�[��������I�v
�u����ȃL�~���f�G�v�ƌ��ɒu���ꂽ����ƁA���x�̓u���[�U�[�̋����������������B
�u�u���[�U�[��������I
�@���Z�����ƈꏏ�ɂ����Ȃ�A������Ƃ͋C���g���Ă���������I
�@�����A���Z�����A�p�Y���l�ɂ���������Ă��ł����!?�v
�u�c����b�c����Ȃ��Ă��c���A�m��Ȃ��������āc�b�v
�g�p�Y���h�Ƃ́y�t�H���Z�i�z�ׂ鍑���̎��ł���A
�����̉��ł���Ȃ���A�Љ�����������畺�𗦂��ēG�n�֏�荞�ޗE��������A
�������g�p�Y���h�Ə̂�����܂łɎ������̂��B
������A�������\�\�g���q�S���q�i���C�I���E�n�[�e�B�X�g�j�h�ƈ،h���ꂽ���`���[�h�W���֑T������Ă��炾���B
�u�����ɂ͎��v�����Ă������ł���!?
�@�Ȃ�Ŋm�F���Ȃ�������!?�@�̎��Ԃ������30���ȏ���o���Ă邶��Ȃ��I
�@�Ƃ����ɂ���ɓ��������Ƃ���l���Ă���A����̐l���Ƃ܂ł��}���ɗ��ăb�I�v
�u�c���������Ȃ��c�B
�@���Ȃ�A���́A���̃I�b�T�����c�B
�@�p�Y�������Ȃ��m��˂����A
�@����ȃI�b�T���A�ǂ��҂��������Ēm������������˂���v
�u�܂����������R�g�����I�@����͂��̍��̉��l�Ȃ�H
�@�Ƃ��Ă��̂��l�ɂ���Ȍ��̕�����������w���b�I�x�ł����!?
�@�c�u���[�U�[��������������������������I�v
�u������Ȃ��c�É��Ƃ̑�Ȗ������ۂ����Ж_�S�����܂��Ȃ�āA
�@���A�����R�m�c���i����˂����c�B
�@���킟�[�c�����A�o������A��i�ɓ{�����A��c�v
�����̌N�։�����ԏサ�A�L���̎p�����������ڈ���̃`�����X�ł���Ɋւ�炸�A
���̃u���[�U�[�́A���̒����ɍݐЂ���R�m�ł���Ȃ���A
�f�������̕s�͂��ֈꖇ����ł��܂����V���b�N�ɓ��]���Ă��Ă���ǂ���ł͖��������B
�u�Ƃɂ����b!!
�@�x������������̂͂����ǂ����悤���Ȃ�����A
�@���̂܂ܒ��ڂ���֍s���R�g�b�I
�@�łȂ��ƁA���`�ꂳ�c���@�C�n���_�[�����Đm���������Ă邩��ˁI�v
�u�c�s���Ă��s���Ȃ��Ă��A�ǂ݂̂��m�������ƃV�S�L�͊m�肶��˂����A
�@�T�{�b�Ēx���������_�ł�v
�u�T�{�b�Ēx���������{�l�����l���݂����Ɍ���Ȃ��́I
�@�\�\�ق炟�I�@�������ƍs����!!�v
�u�͂��͂��c�c�c�������A���₩�܂����g�R�����A������Ɏ��₪�����ȁc�v
���₩�܂������ɐӂߗ��Ă�ꂽ�f�������́A�ϔO�����悤�ɖ{�����x�ڂ��̗��ߑ���f���A
�������s�������ɐ݂���ꂽ�x���`�֗��Ă����������̓�����g�ɒ������B
�����ƌĂԂɂ͂������ɂ��e��ȃV���G�b�g�����A����ł��p�[�J�[�ƃW�[���Y�݂̂ʼn���֏o���������A
�����ƃ}�V�Ȋ��D�ł���B
�S�d���݂̃o���_�i�ƃu���X�g�v���[�g�A���r���ł߂�拭�ȃK���g���b�g�A
�����āA�g�̏�ȏ�̒�����30cm�ȏ�̑������ւ鋐���E�c���@�C�n���_�[��
�x���h�z���Ɍ��֊|�������̎p�́A�ԈႢ�Ȃ������̗b�����̂��̂ł���B
�u�c�c�c�c�c�c�`�b�v
��ł����Ȃ���A�Ō�Ɏc�����\�[�h�x���h�����X�����ɒ��߂�ƁA�f�������́g�����h�͊����������B
�\�[�h�x���g�̍����ɂ́A��������̕z�ŕ�ݍ��݁A
�X�ɏォ��v���̃x���g�Ŋ�d�ɂ����ꂽ���̂���Ă���B
��������@����ɒ����������Ǝv���邪�A�����Ĕ����Ȃ��悤�ɕ���Ă���ӂ�A
�f�������Ȃ�̎v������̈�i�Ȃ̂��낤�B
�u�ق�A�����~�܂��Ă��I�@�}���A�}�����I�v
�u�c�`�b�c�v
���x�̐�ł��͖��炩�Ɍ����邳�������������̂����A
�����֗��܂蕶���R�炵�Ă����Ԃ̍D�]���]�߂Ȃ��ȏ�A
�ς킵���Ȃ�����E�F���f�B�̌����ʂ�ɂ��邵���Ȃ��B
���X�������ɔw����܂�A�p���������x�����x����ł���R�炵�Ȃ���A
�悤�₭�f�������͖̉���֑��������n�߂��B
�u�c�������I�@�z���g�A�������Ȃ�����Ȃ�ɂ��ł��Ȃ�������I�v
�u����ɂ�����A�S�ʓI�Ɏ���c�ɐU�点�Ă��炤��v
�u�e�F��������A����ȏ�Ȃ��j�ɐ��艺����Ȃ��悤�ɁA
�@�u���[�U�[������C�������Ă���Ă����������ĂI�v
�u���A����A���́c���A���A���������A�É����X�̏����Ȃ�āA
�@�f�������̓z�A�Ȃɂ���炩�����̂��ȃb�H�v
�u�����R�m�c�̃N�Z�ɁA����Ȏ����m��Ȃ���ł������H�v
�u�m���Ă���A�������̉������ăP������ď�����킹���c�v
����̈����b�������ւ��悤�Ƃ����u���[�U�[�̖ژ_���̓o�b�T����̂Ă��A
�E�F���f�B�̓{��ɖ��𒍂����ʂɂȂ��Ă��܂����B
����ł́A�����g�R����������ǂ��납�A�s�͂��ȌZ��e�F�Ƃ��ď��f�ł��Ȃ��_���j�ł���B
�u�c�z���g���ǂ����B
�@���Ɍ������Ǝ��肪�����Ȃ��Ȃ�Ƃ���A
�@���Z���������ł�������v
�u�c�Ԃ����t�������c�v
�Ў�Ő�����Ȃ����炢�̗��ꂽ�E�F���f�B�ɂ�荞�߂��A�u���[�U�[�͗��_���Ă��܂��B
�܂��܂��_���j�̎p�ł���B
�u�\�\�Ȃ��悭�킩��܂��ǁA
�@�܂����d���̘b���Ǝv���܂��B
�@�w���̉҂��͌�q����x�c�Ƃ��Ȃ�Ƃ���s���Ă܂�������A
�@���O�ɖ�������莆�ǂ�Łv
�t���[�����X�̗b���ƋƂŐ��v�𗧂Ă�f���������A
�18�Ȃ���A�b�����Ԃ̊Ԃł͊��ɐ��r�Ɩڂ������̋Z�ʂ����ނ𗊂�ɁA
�l�݂̂Ȃ炸�e��@�l����̈˗������₽�Ȃ��B
�u��q�̈˗��c���B
�@�����X�^�[�̓����ɔ�ׂāA�����������Ȃ�����Ȃ��B
�@�f���������u�[�����p����ɕ����Ԃ�v
���ӂ̃c���@�C�n���_�[���ő���ɐ�������퓬�s�ׂ���Ƃ��Ĉ����Ă��邪�A
�A�K���ɂ���Ă͌�q�╨�i�̔����Ƃ������˗������������B
�����������A�d�����I�������́A���u�܂�˂��v�A���u�\�ꑫ��˂��v��
�s���S�R�Ă�Q���̂��킾�B�����ƍ�����������낤�B
���H�b���݂������L�[���Ȃ���ɃY�{���̃|�P�b�g�֗����˂����݁A
�̐�����舕�����f��������������A�������������ʂɋ�����l�ɂ́A
���x�̔C�����A���̗��̎n�܂肪�A
�₪�Đ��E�́y�U��z��\�����Ă�قǂ̐킢�֔��W����Ƃ́A�m��R�������\�\�\�\�\�\
��
�����̍��y�t�H���Z�i�z�B
�[���N�₩�ɖq�̓I�ȍʂ�̊X���݂ւ������R�ɗn�����ތy�Z�̋R�m�����́A
�L���Ƃ���t���v���[�g�A�[�}�[�i�S�g�b�h�j�ɐg����Ő�n�֕������낤���A
�����̂��̍��ɂ����ẮA�y�ƍ߂̎����܂�Ƃ����ȒP�ȏ�紂��炢�������鎖�������A
�C���̓r���ɗ�����������X�X�Œ��̐l�X�ƒk����p���悭��������B
�E���Ӗ��Ƃ��v������̂́A���ꂾ���y�t�H���Z�i�z�����a�ł���Ƃ��������̏؋����B
�i�c�c�c�܂��T�{�b�Ă₪��ȁB����ł悭�얯���Ƃ������������j
�g�X���݂ւ������R�ɗn�����ށh������M����悤�ɁA�y�t�H���Z�i�z�́A
���E�ł��ނ����Ȃ��R�m�̍��Ƃ��Ă��m���A�y�Љ�z�֑����̋C�z������A
���z�������Ĉ��̉��E�ݎ��y�Љ�`�z�̌���W�Ԃ��Ă����B
�u���A�`�X�A�f����������I�@�y�t�H���Z�i�z�ɖ߂��Ă���X�ˁI�v
�u�c�c�c���H�@�N���A���O�H�v
�u����A������Ɓ`�A���̃L�Y�܂ŖY��Ȃ��ł���������I
�@���I�@�����A���E�K���x���W�����X!!�v
�u�\�\�\�����A�u���[�U�[��g�R�̃n�i�^�����v
�u���߂āA�`�X�A�f����������b!!�v
�u�������Ȃ��A���O�́c�c�c�B�Ȃ�ł���ȃ��_�Ƀe���V����������c�c�c�v
���̏Z�l�ƒk���Ă����Ⴂ�R�m���琺��������ꂽ�f�������́A
�ŏ��A�ނ����҂��s���Ɨ����ɒN�����Ă��܂������A�璆�ɓ\��t����ꂽ�J�n�p�ɂ����
�悤�₭�L���̎��������鎖���o�����B
�y�����R�m�c�z�Ȃ�E�܂������̂��f����y�t�H���Z�i�z�̋R�m�c�֏������Ă���
�c�F�B�̃u���[�U�[�Ƃ̉��̂�����A�f�������͓x�X���R�m�����m�Â����Ă���Ă����B
�w�����A���E�K���x���W���x�Ɩ�������N�����̓��̈�l�ŁA�������C�����͋������̂̌��̘r�O�͎l���l�O�B
���̊Ԃ����킳�Ȃ���̖͋[��Ńf�������ɃR�e���p�ɂ̂��ꂽ���肾�����B
�u�f����������A���A�q�}���X���H
�@�����A���Ȃ�A���ƈꏟ���荇�킹���Ă���܂���H
�@���I�@�V�����K�E�Z�v����������āI�v
�u���̋R�m���V�����ŗ����˂��������Ă�˂����B
�@�q�}���ė]���������������A���B
�@�������͂Ă߂���̑叫�ɌĂ�Ă���ǂ�����˂��v
�u�É��ɁH�@�܂��d�����X���H�v
�u�����ȁc�c�c�v
�u���A����H�@�f����������H�v
�u����ȂɐV�Z�����������A���R�����ł��s���ȁB
�@�����Ƃǂ����̃E�X���o�J���D���Ȃ��������肵�Ă���邾�낤���v
�Ȃ����b�𑱂��������ȎႢ�R�m��u���Ă��ڂ�ɁA
�f�������̑��͂��Ăт̂�����������i��ł����B
�u�����A�f�̎��I�@�ߍ��܂��g�̂��K�b�V�����ė�����˂����H�v
�u�f�̎����ČĂԂȂ��đO���猾���Ă�I
�@�ق��ċ������Ă��A�����悧�I�v
�u����ς�����������ĂȂ��Ŗ�����H�ׁI
�@�E�F���f�B�������������Ă���B�o�J�Z�̃o�����X�ň��ȐH�������ǂ��ɂ����������āv
�u���̑���Ɍ����Ă���Ă���A�I�o�����B
�@�o�����X�̗ǂ��H�����Ȃ��Ă���p���[�s���ł��ꂿ�܂����Ă�B
�@�b�����������́A�J�����[���ʏ�����łˁv
�u���������A�����������̂ĂȂ�ˁ[�ȁI�@�f�����V�̓E�`�̂����ӂ����H
�@�����A�f�����V�I�@���S���̚���ȂV�J�g���ē��H���A���I
�@���H���Ă��A�X�e���̌��݂Ă��Ƀh�J���Ƌ����Ȃ炟�b�I�v
�u�P�b�c�c�c�A�N�\�o�o�@�݂Ă��ȉ������ɂȂ邭�炢�Ȃ�A������A������v
�[�ΑN�₩�ȐA�Ɉ͂܂ꂽ����������ɂ́A���C�Ɉ��鏤�X�X��ʂ�K�v������B
�e���V�����̒Ⴂ�f�������ɂ́A�����ł������X�X�̌����͔ς킵���̂ɁA
���̏�A�ނ������ȍ�����悭�m��l�X�ɐ����|������̂����炽�܂�Ȃ��B
�i�Ȃɂ��g�f�����V����h�c�c�c���������A���܂�˂����c�c�c�������悧�`�j
���ԂɊ����ᰂ��O�`���O�`���ɂȂ�Ȃ����ɏ��X�X���삯�����Ă��܂����B
��������Ηǂ����̂��A�|�����鐺�֗��V�ɓ����Ă����f�������́A
�ނ�ɋC�t����Ȃ��悤�ɂ����Ɨ��ߑ���f���̂Ă��B
��
�u�y�t�H���Z�i�z�ɂ͂������ꂽ���ȁH
�@���K�̈Ⴂ�ɂ�鍷�ق͂��邩������A
�@����̋@�\�ɖ������Ă���������K���Ȃ̂����c�v
�u�����K�v��������A�������������܂���B
�@�c�G�n�ɍ݂��Ė��f����ȂǁA��m�ɂƂ��Ēp���ׂ����ł�����v
�u�G�n�c�c�c���B
�@���̂悤�ɋl����̂������̖����b���c�v
�c�����w�G�n�x�Ƌl���A���G�����Ɍ�����c�߂�g�p�Y���h�̋ʍ��։y������l���́A
����̔C����C����鏭�N�b���ł͂Ȃ��A
�ӏ����{���ꂽ�~�X������̒����\�\�����y�s�i�J�z�ƈ����\�\���g�������߂̏����B
�_�炩�ȍ��F�̃u���E�X�ƒW���O���[���̃����O�X�J�[�g�̒g�F��h��Ԃ��悤��
�r�����v�킹��u���b�N���U�[�̃R�[�g���H�D��A
�ꍑ�̉���O�ɂ��ęz�R�Ƌ����፷���������鏭���������B
�u����ɂ��Ă��������ȁA
�@�ˑR�A���Ȃ����y�t�H���Z�i�z�Ɏp�����������́c�v
�u�̎Z�ɘj��A��X�̕ی�𑣂����ȂՂ��Ă���܂�������c�B
�@�{���Ȃ�A�G���Ɉ˂�ȂǁA����ȏ�̒p�J�͂���܂��A
�@�������䂦�A�����ĊÌ��ɏ�点�Ă��������܂����v
�u��X�����Ȃ������֓������s�ׂ́A������掂��Ă��d�l�̖����������B
�@�ے�͂��܂��c�c�c���܂����A
�@���̌��ӂ�P���Ȃ��Ă܂Ŏ��̂��Ƃ֎Q��˂Ȃ�Ȃ������m�������A
�@�ނ̒n�܂ł̌�q�ƌ��킸�A�䂪�y�t�H���Z�i�z�ɂĂ��Ȃ���ی삵�A
�@�K���₻�Ȃ��́\�\�v
�u�]�ވȏ�̉���G���֏d�˂����͂������܂���B
�@���ǂ������C�����Ȃ�A���̈ӂ�����ł��@���肢�������̂ł������܂��v
�u�c�c�c�c�c�c�c�c�c�v
�������܂ŐL�т��A�F�f�̔����u�����h���̐���ᑐ�F�̃��{���Ŕ���A
�z�ɂ̓Z���t�B�i�C�g�̋ʐA�E�T�C�h�ɂ͏����ȉH������B
��16�Ƃ����N����̑����i���A�b�h���Ȃ���ɍd���ȁg�r���h�̑O�ɂ͂��̈��炵����N�H����Ă���B
�\�\����A�g�r���h�]�X�͊W�Ȃ��A�ޏ������ߑs�Ȃ܂ł̋����፷���̑O�ɁA
16�Ƃ����������{�����ׂ����炵���̑S�Ă�����t���Ă��܂��Ă����B
�u�c����͂����ƁA�@���̓x�A���s�֓�������������������ɂ��āA
�@�\�߂��������Ă��������̂ł����c�v
���ĕt�����͈̂��炵�������ł͂Ȃ��A���̊፷�����A�\������B
����Љ�̐��`����g�p�Y���h��O�ɁA�圤�ȑԓx���B�����Ƃ����Ȃ��B
�ʍ�����삷��߉q���c�̔w�������Ȃ�قǂɁA�ǂ��܂ł��圤�ɁB
�u�y����z�c�̓���ŋ������b���������m���ȁH�v
�u�c�L���E�K�H�@�����A���ɂ������A�������܂���v
�u�c���莝���ȊO�ł͓���g�����Ȃ��ʋ����E�c���@�C�n���_�[���Ƃ���A
�@���̃t�@�C�^�[�i��m�j�ٖ̈�����B���r�͕ۏ���B
�@�c�g�ֈ��ɋ����Ӊ�h�ٖ̈��ʂ�A���X�Ȃ�ʍr���C�����ʂ��ꂾ���A�ȁv
�u�g�p�Y���h���X�̐����Ȃ�A��w�ɘr�̗���m�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�@�c�T�֒u���ɂ͖��̉߂�����Ɂv
�u�g�T�֒u���ɂ͖��Ȏ荇���������t�������h�c�Ȃ�Ƃ�����ɋ������̂��ȁv
�u����̂���ł������܂�����v
�ɂ���Ƃ����Ȃ��������̏����̑ԓx�ɁA�p�Y�������R�炵�����A
�ʍ����ɕs���Ȃ��Ȃ萺�������n�����B
�u���B�ȁA�I�b�T���B��������x�������܂������v
���ɂ���������������͈ꍑ�̉��ł���B
�ɂ��ւ�炸�A�Y�J�Y�J�Ɩ���@�ɓ����Ă�����m���̏��N�́A
�O����ʼnp�Y�����ɂ߂��A�K�������������w�̎��ɘc�Ȃ����A
�܂�ŋߏ��̘V�l�֘b��������悤�ȑԓx�ƌ������B
�u���̊Ԃ͔��������Ɠ�����ꂽ���A�����͈ꎞ�Ԃōς��B
�@���Ă̓E�F���f�B�ɐK��@���ꂽ�ȁA�f�������H�v
�u�������ȁc�l���Ƃ̎���ɂ܂Ŏ�˂�����ł���Ȃ�B
�@�������Ɨp�������������Ă����B
�@�����A���������܂����ꏊ���Ă̂���̋��Ȃ�łˁv
�u�S���܂��Ă���O�������Ă��A�����͂Ɍ�����s�������H�v
�u���������ׂ����I�b�T�����ȁc�B
�@��������A�������Ƙb�i�߂����I�v
�y����z�Ƌw������鏊�Ȃł���c���@�C�n���_�[��w�������f��������
�p�Y���̔���ɑ��A���������Ă����ۂ��������B
�ꍑ�̉��ɔq�y����l�Ԃɂ͂���܂����s���ȑԓx�����A
�p�Y���͂��납�A�߉q���c������A����ȏ�ə�߂Ȃ��̂�����A���ł����̒��q�Ȃ̂��낤�B
����ȐM�����������i�ɋ����A���ꂽ�悤�Ɋ��������u�����h�̏����̎����ɋC�t����A
�f�������́u������������˂��v�Ƃ�����˂�@�������B
�u���炱��c���܂薳�V�Ɉ������̂ł͂Ȃ����A�f�������B
�@������̏��������A����A���O����q���˗�����Ώہc�˗��҂Ȃ̂�����ȁv
�u�c���[�X�E�A�[�N�E�B���h�Ɛ\���܂��B
�@���̓x�͂����Z���ɂ��ւ�炸���ׂ̈Ɍ�q�������Ă��������A
�@���ɂ��肪�Ƃ��������܂��v
�p�Y���̌��t�ɑ�����A�����c���[�X�͗�V���������ȏЉ����A
�˗��҂ƒ������ꑻ��ǂ��납�A�f�������͌y�����������邾���ŁA
�u���[�c�ʂɖ��O�Ȃ�Ăǂ������Ă�����B
�@���܂肫�����A���K�^�C�I�R�g�o������˂��B
�@�ړI�n�ƃA�K���̊z���������Ă�����A����Ȃ�̓����͂��Ă�邩���v
�u�\�\�ȁc���v
�Ȃǂƕs���ǂ��납����ɂ܂�Ȃ����t�𓊂������Ă����̂�����A
����܂ŕX�̂悤�ɕ\�������Ȃ��������[�X�̔����������ɒ݂���B
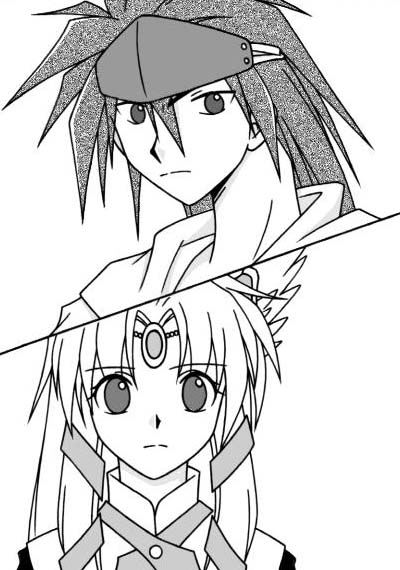
�i�c�c�c�Ȃ�Ď���Ȑl�Ȃ̂ł��傤���c���B����ȕs�͂��҂���z���Ȃ�āA�p�Y�����ǂ������Ă��܂��c���j
�i�c�c�c�h�C�L�F�����ȁc�j
��V���y��f�������ƁA��V���d�郊�[�X�̓�l�́A�܂��ɉƖ��B
�ň��ɍň��ȃt�@�[�X�g�E�C���v���b�V�����ɂ���āA��l�̗��͖����J�����B
�y�{�҂s�n�o�ցz�@�@�@�@�@�m�d�w�s��